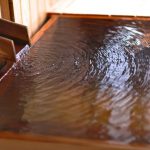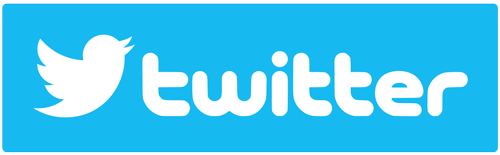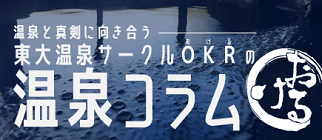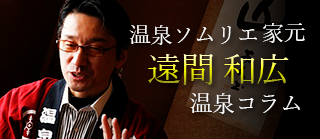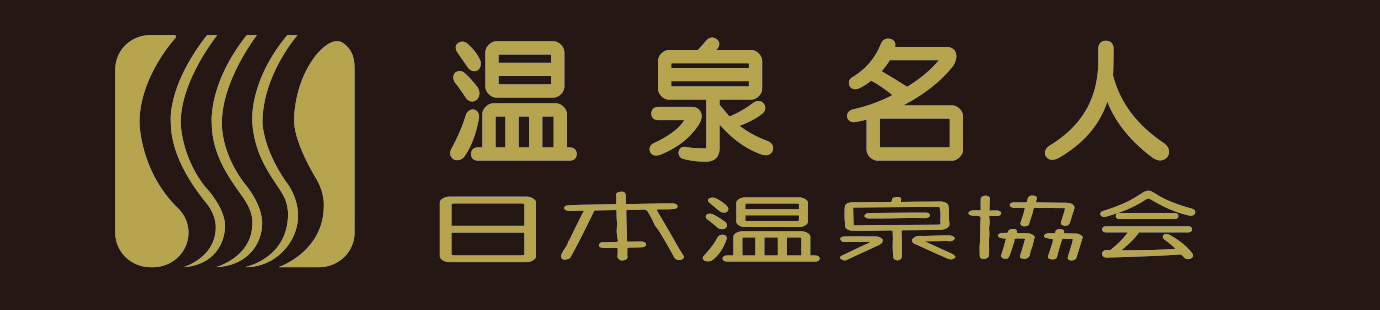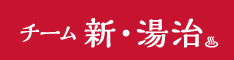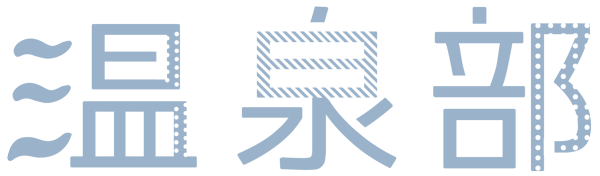新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって観光のあり方が大きく問い直されています。
全国の温泉の最前線で活躍する方にお話を伺い、アフターコロナの温泉文化について考えようと思います。
第2回目は、宮城県 東鳴子温泉で湯治文化をよみがえらせようと、農業体験やワーケーションなど様々な取り組みを精力的に行う、「旅館大沼」5代目湯守の大沼伸治さんにインタビューしました。
大沼さんは、今だからこそ「ソーシャル・オアシス〔現代社会における心のよりどころ〕」としての「湯治場」が必要だと言います。大沼さんが構想するこれからの湯治場とは、どのようなものでしょうか。
目次
湯治場はみんなで大切にしていく「場」

旅館大沼 5代目湯守 大沼 伸治さん
大学卒業後群馬県の旅館で修業を積み、家業を継ぐ。「日本秘湯を守る会」加盟、『ミシュランガイド東北』掲載など、湯治宿として人気を博している。湯治文化を現代社会に引き継ぐべく、農作業と組み合わせた「地大豆湯治」や、ノルディックウォーク、テレワークなど様々な取り組みを展開。東鳴子温泉観光協会長、NPO法人 東鳴子ゆめ会議代表も務める。

聞き手:橋本 惇(温泉部編集長)
東大温泉サークルOKRへの入会を機に温泉に目覚め、在学中に海外も含めて400湯以上をめぐる。大沼さんとは4年以上のおつきあいがあり、様々な影響を受けた。現在は観光関連の仕事をしている。
コロナをきっかけに観光のあり方が大きく変わろうとしていますが、”すべてがコロナのせい” とは言えないように思います。
「コロナ前」から起こっていた小さな変化がメインストリームになっていく部分も大きいのではないか、と。
これまでは移動が自由にできて、好きなところに遊びに行けましたよね。
コロナによってそれが鈍化し、人々は行くところを選ぶようになると思います。
何のためにいくのか、それはどんなところなのか、そこで何をするのか──以前よりも意識して目的地や宿を選ぶようになるのではないでしょうか。
コロナ前よりもいっそう「選ばれる宿」であることが大切になるということですね。
大沼さんが築いてきたお客様との強固な関係も選ばれる理由になると思います。
3月のマスクが一番足りていないときにマスクが手に入ったので、お得意様に送りました。
ここを成り立たせているのはお客様です。だから、お客様の役に立つことをしようと思いました。
「旅館こそ大変なのに、どうしてそこまでしてくれるの」とか「本当にありがとう」といったメッセージをもらって、お互いの思いをあらためて感じられました。
お客様ー旅館という関係よりも、みんなでここを大切にしようという関係になっていくんのではないでしょうか。
大沼さんはよく、「場」という言葉を使いますよね。
旅館ではなく、ここに来たいと思ってくれる「場」でありたいと思っています。
自分たちが守ってきた「場」であるとともに、お客様にとっても疲れた時に行きたいと思う「場」ですね。
宿をやる人とお客様のどちらにとっても大切な「場」になると良いですよね。
緊急事態宣言下で旅行に行けないときに、前払い宿泊券を買って応援する「種プロジェクト」に参加されて、多くの支援とあたたかいメッセージが寄せられていましたね。
私も事務局のお手伝いをさせていただき、暖かいメッセージに思わずほろりとしてしまいました。
種プロジェクトには、割引やプレミアムなどの特典はないけど、本当に多くの人が応援してくれました。本当にありがたかったです。
今までたくさんの方々に見守られてきたことを痛感しました。
未来の宿泊に今払う。コロナ禍に苦しむ温泉旅館を応援する「種プロジェクト」

なくなってはじめて大切さに気づくことってありますよね。自由に温泉に行けなくなって、あらためて温泉のありがたみをひしひしと感じました。
大好きな温泉にいけなくなったら寂しく思う人は多いでしょう。
〔長期滞在で療養する昔ながらの〕湯治場のようなディープな習慣はあまり残っていませんが、”なじみ” の宿にたまに行くという点では今も変わらず湯治だと思います。まさに湯治ですね──くり返し来てお湯につかるという点では。
コロナによってお客様をより身近に感じましたし、お客様に当館の思いもお伝えできたと思います。
アフターコロナの旅行は、自分にとって必要なところに行くようになるのではないでしょうか。常に違うところを探す旅ではなく、自分に必要なところを求めていく。移動が困難な時代だからこそ、そうなると思います。
これまでの観光は、主客がはっきりしていて消費的な意味合いが強かったように思います。これからはお互いに持続可能な温泉にしていくために、どのようにしていくか考えていかなければならないですね。
安心して過ごせる「ふるさと」としての湯治場

旅館大沼のお湯には、とにかく癒やされる。
お客さんの期待に応えようとするあまりに、長時間労働や低い生産性などの課題を抱え、人手不足に苦しむ旅館も少なくありません。
温泉地や温泉旅館が持続的であるためにも、宿とお客様との関係も変わっていくのかもしれません。
お客様と新しい価値を共創していきたいと考えています。
橋本くんたち東大温泉サークルOKRがやってた「ふるさととしての湯治場」は大切なテーマですよね。
橋本くんのような東京出身で「ふるさと」がない人だけでなく、ふるさとがある人にとっても、第二、第三のふるさとがあっていいと思います。
人も自然も、サードプレイス〔家庭と職場・学校に次ぐ「第三の居場所」〕をこえて、もっと重層的になっていくのではないでしょうか。
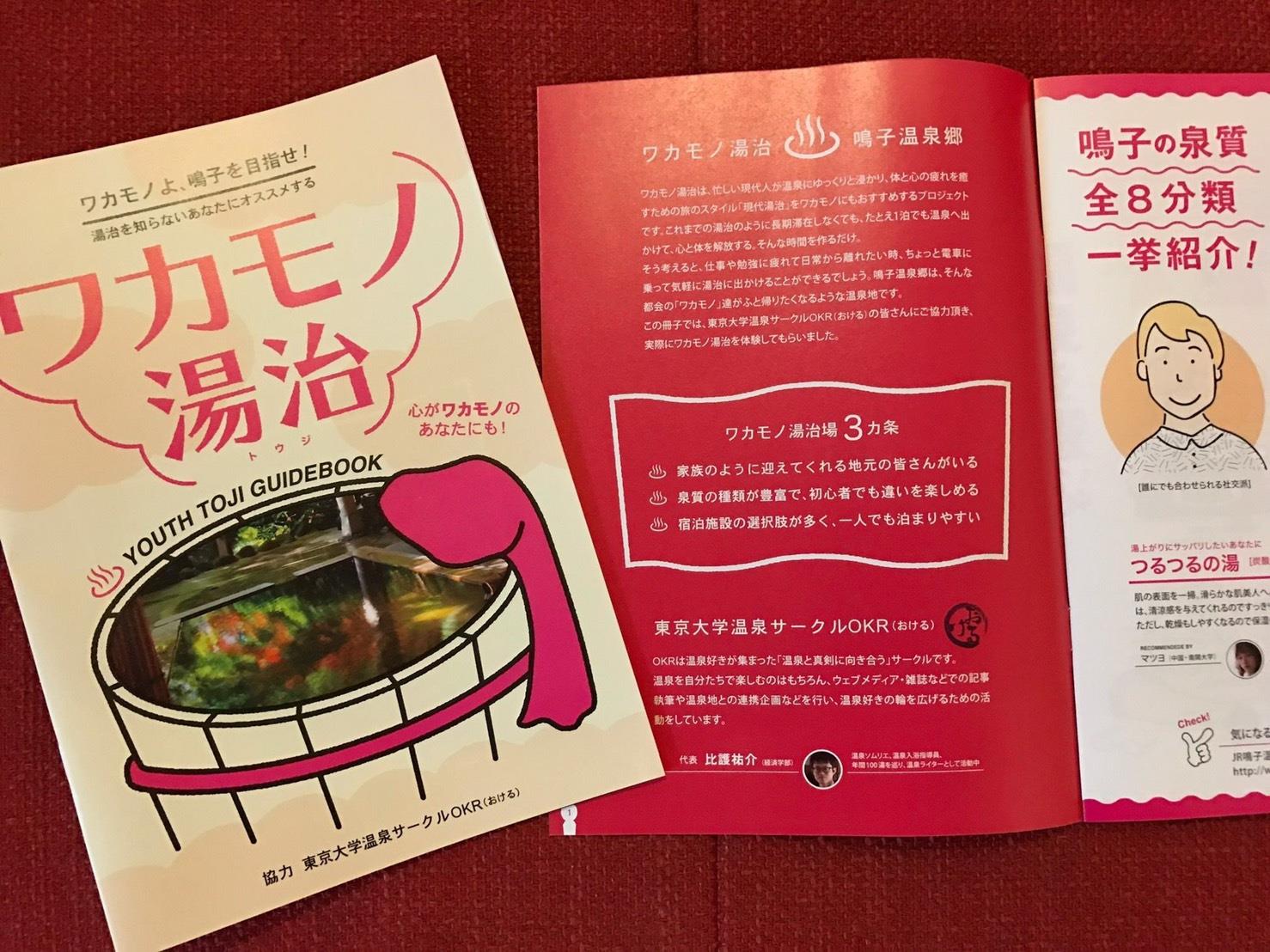
東大温泉サークルOKRは2016年から「鳴子ワカモノ湯治」プロジェクトに取り組む。17年にはパンフレットを作成した。
「ふるさと」に集う全員がそこを大切に守っていこうと思うようになるということですね。
コロナを機に、安心・安全を確保しつつも、「ふるさと」を求める人は増えるでしょう。鳴子に限らず、その人なりのふるさとがきっと見つかるのではないでしょうか。
ふるさとには主客はなくて、みんなで大切にする場所。私は旅館に生まれた者としてここの源泉を大切に守ってきました。より価値のあるものとして、皆さんとともに守っていきたいと思います。

東鳴子の温泉街は、レトロで落ち着く雰囲気。
もちろん感染症対策こそが今第一に問われる安心・安全ですが、ウィズコロナ・アフターコロナにおいては精神的な意味での安心・安全もいっそう求められるようになると思います。
そこでふるさとのような宿が求められるということですね。
温泉地や温泉旅館の困っていることがあれば、手伝ってみるのもいいと思います。敷居の高かった温泉旅館もより身近に感じられるはずです。
東大温泉サークルOKRの人たちも、よく宿のお手伝いをしてくれましたね。
草取りや雪かきなど、都会で暮らしているとなかなかできない体験で楽しかったです(笑)。
殻を破れば無限の可能性:温泉旅館×ワーケーションなどにも挑戦

東鳴子温泉・旅館大沼「一汁三菜プラン」の朝食(一例)
まず、自分や自分の宿のオリジナリティを考えてみることが大事だと思います。
部屋や食事、温泉といった、既にもっているものを活かして、地域のリソースと合わせてどう創っていくか。旅館という枠に縛られずに発想したいです。
大沼さんは、テレワークプランの造成やワーケーション〔テレワークとバケーションを組み合わせた長期滞在〕の実証実験にも積極的に取り組まれています。
宿のサービスを分解して考える中で思いつきました。パッケージで考えるのをやめて、旅館という殻を破れば可能性が広がると思います。
今はやりのワーケーションも、その中のひとつのコンテンツとして考えれば自然ではないでしょうか。
ワーケーションの実証実験では、やりながら考えていってます。どういう仕事が、どういう人がやりやすいのか、これから考えていく。
そして、いくらエビデンスがあってもドラマ設定がないと面白くないですよね。お客様の癒やされたいという思いにも応えたいです。
在宅勤務を認めていても、ほかの場所での仕事を認めていない企業もあります。そうした企業はワーケーションに対して、「ちゃんと仕事ができるのか」という懸念があるのではないでしょうか。
1週間のうち3日寝て過ごしてもいいわけですよね(笑)。働く人の気持ちに寄り添わないといけないし、仕事の時間ではなくて成果で評価するように変わっていってほしいです。
「良い仕事をするために、これくらいまでは休んでもいい」といった基準も、実験の中で見えてくるのではないでしょうか。
湯治場でやることによって、健康をつくりながら仕事するわけですよね。ただ単にリフレッシュするだけではなく、腰痛や眼精疲労が良くなるみたいなのがあったほうが嬉しいはずです。
せっかく鳴子という湯治場でやるのですから、昔から心身を癒やしてきた日本の文化を活かすほうが合っていると思います。
ソトの生活では見えてこなかった自分の内面に、湯治場で向き合う

2019年9月に行われた「湯治ウィーク」では、1週間にわたって18もの手作りイベントが開催された。
今はどうしても、倒れるまでケアしてくれないというか、未病〔まだ病気として現れていない心身の不調〕を治す習慣がないですよね。
一回倒れてしまうと大変ですよね。「転ばぬ先の杖」に湯治がなればいいと思います。
まさに「ピットイン」〔カーレースの途中でメンテナンスのため必要な停車〕ですね。
昨年東鳴子温泉で講演されていた、仙台ペインクリニック石巻分院長の川合先生の使われているたとえですね。
9/23〜湯治ウィーク開催!宮城県東鳴子温泉・川渡温泉で「湯市マルシェ」「お得な限定プラン」登場

コロナで外出できなくなって癒やされる場所が家になりましたが、なかなか休まらないですよね。
日常を離れるのが湯治の大前提です。転地効果〔日常と異なる環境に身を置き心身に適度な刺激を与えることで得られる効果〕は大事ですよね。それから時間軸。
日常を離れて温泉に入る、とてもシンプルなことです。
「時間軸」とおっしゃったのは、やはり1週間とか2週間とか、気長に過ごすということですよね。今の働き方ではなかなか厳しいような気もします。
もちろん1泊でも2泊でも大歓迎ですが、本気の人には湯あたりするくらいいてほしいですね。
反転作用〔温泉療養の途中で一時的に体調が悪化すること。好転の予兆とされる〕は一つの洗礼のようで、「体験しないで帰るのはもったいないよ」って。
湯あたりするくらい〔4~5日目〕が一つの目安になるといいかなと思うのですが、湯あたりという現象があるってお医者さんに話すとびっくりされますね。
一度体調が悪くなってから良くなるって聞いたことないって言われます。
気長に待たないといけないですね。
やっぱり時間軸ですね。そう考えると、職場を離れていても仕事できるようになってきてるのはいい流れです。
体調に関連してですが、自粛でずっと家にいると、自分の体調の細かな変化に敏感になった気がします。
観光は外向きだけど、湯治は内向きだと私は思っています。2012年から “retreat〔日常生活を離れてセルフケアをする転地療法の一種〕” にも取り組んでいて、今こそ “retreat” の時代だと感じます。自然の中にパラっと散って自分に向き合う。
なぜ日常を離れるかというと、寝てるとき以外はソトの世界で生きてるじゃないですか、仕事とか家庭とか。
一人になると自分と向き合う時間が自然と増えますよね。自分の体のこととか、日常生活のことを思索したり。
日常の些末なことで押しやられて畳まれてたことがニョキニョキ出てくるわけです。考える時間が必要ですよね。
一番いいのは「何も考えない」ことですが、それは難しい。だから、坐禅や瞑想をプログラムとして体験してもらうのもいいと思います。
今までの旅行は物見遊山で、ソトのものをいかに自分に取り込むかでした。これからは自分の内面に向き合うのを率先してやっていきたいです。

収穫したばかりの新鮮な枝豆をみんなで食べるのが「地大豆湯治」の醍醐味。
大沼さんが2004年から取り組まれている「地大豆湯治」では、農作業それ自体を楽しむだけでなく日頃のストレスを「放電」することもコンセプトに掲げています。
観光旅行って「充電」のイメージがありませんか?
でもその前に、たまってるものをお湯に流さないといけない。出さないと新しいものが入ってこないですよね。放電の中でエネルギーが入ってきます。
「呼吸」もそうですよね。 「呼」が先で、「吸」があと。必ず先に出すわけです。この順番でやると元気になるのです。
アース(放電)ってまさに土〔英語でearth〕で、自然とふれあって温泉で流してもらうのは最高の命の再生でもあるわけです。理屈抜きで気持ちいいですよね。
やっぱり大沼さんがコロナ前から取り組まれていたことの多くが、アフターコロナの湯治文化につながるのを感じます。
キーワードはいくつかあります。
まずは家族や従業員を大切にして、それからどういう人が大切にしてくれているのか考えるといいと思います。そして、土地ならではのおもてなしをしていく。
「唯一無二」を考えたほうがいいですよね。
場所が違い、歴史が違い、人も違うわけで、すでにどの旅館もオリジナルなのです。
「プラットフォーム」と「ソーシャルオアシス」が湯治場の未来像

2019年の「湯治ウィーク」では様々な手作りイベントが行われ、新たな交流も生まれた。
大沼さんはこれからの湯治場を、各々がやりたいことをする「プラットフォーム」だとおっしゃっていましたね。旅先で何かをするのは、日常ソトの生活で忙しい人にとっては慣れないかもしれません。
自分の内面に向き合って、やりたいことをもっている人が少しでも増えてくれたら嬉しいですね。
それから大沼さんは、「ソーシャルオアシス」という概念も提唱されていますね。湯治場が現代社会の中でオアシスの役割を果たすという考え方です。
泉(オアシス)はみんなが大事につかっていくものです。
みんなでよい場所にしていく場であってほしいですね。そうなってくるともはや旅館じゃないですが(笑)。そういう意識をもって旅館の人たちも参加していいと思います。
ちょっとしたお手伝いをお客さんにも協力してもらうような関係も、嬉しく感じる人はいるはずです。
僕なんかは、脱いだ浴衣を散らかさないとか、ちょっとした気遣いをしたい方ですね。
そういう風にみんなで使うと気持ちいいですよね。湯治場はプラットフォームであって、交流の場でもあります。
互助や利他の精神が大切になるでしょう。
コロナ対策では、従業員の安全が守られてこそお店が成り立つってことと、お客さんも感染拡大対策に協力するのが不可欠だってことがしっかり定着しました。
サービス業にとっては結構画期的な考え方なんじゃないかなって思っています。
まさに「場」ですね。お互いが「場」に貢献して成り立たせていく。
一気に世の中が変わるわけではないですが、そういうところが少しずつ増えていくのがいいんじゃないかなと思います。
ゲストハウスのような共有スペースが多い宿では、騒いだり汚したりできないですよね。湯治場も同じ。調理場やお風呂など、共有スペースが結構多いですよね。

自炊するのも湯治場での過ごし方の一つ。
意外とそういうところが若者にウケたりしていますよね。僕もゲストハウスにはよく泊まります。
他人と「場」を共有すると、「あ、今騒いだら迷惑だな」とか、いろんな気づきの場面がありますよね。もちろんただお客さんに協力してもらうだけではなくて、お互いに楽しいやり方でありたいですが。
残すものは残しつつも、宿の文化は変わっていかないといけないと思います。
最後に温泉好きの読者のみなさんにメッセージをお願いします。
まずはお互いに感染に気をつけて楽しんでください。
温泉に入ればやっぱり気持ちいいですよね。健康づくりの一環として、湯治にチャレンジしてもらうのもいいと思います。
そして、「ふるさと」を見つけて、いざというときにそこに行って自分を整えられる場所があるといいと思います。人とか地域とかも、お湯とともになじんでいく中で、深みを知ることができるでしょう。
これからの時代、何があるかわかりません。旅館大沼では、第二次世界大戦のときには東京都台東区の小学生たちが疎開してきました。震災のときには、津波で家を失った人を受け入れました。
安心・安全な自分のふるさととしての温泉地をもっておくのは大事なことだと思います。
先が見通せず、ストレスも多い現代社会を生きる上で、自分にとって安心できる「ふるさと」のような場所があると、疲れた時にすぐに自分を癒やすことができますよね。
ここには農業・エネルギー・水・仕事環境、すべてがそろっているので、可能性に満ちていると感じます。私は気分転換以外どこに行きたいって思わないですね(笑)。そしてここは、ある意味修業の場でもあると感じています。
アフターコロナに向けて、まだまだ進化を続けていきそうです。これからもどうぞよろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
まとめ:人々が集う「場」としての湯治場

旅館大沼の名物「千人風呂」にはやさしい表情をした天女の絵が描かれている。
サバンナのオアシスに集う動物は、水をめぐって争うことはありません。しばし休息し、ふたたびそれぞれのすみかへと戻っていきます。
大沼さんから「ソーシャルオアシス」の言葉を最初に伺ったときに、こんなイメージが頭に浮かびました。
ストレスの多い現代社会にあって、日常生活を離れて日々背負っている役割から解放される場を必要としている人はきっと多いはず。
湯治場の「三養」のうち、病気を治す「療養」は西洋医学にとってかわられましたが、「保養」「休養」こそ現代人に最も必要であり、湯治場が得意とすることではないでしょうか。
日常と異なる場所でありながら、安心して自分自身と向き合ったり、普段できないことをやってみたり。物見遊山の旅行が目指す「非日常」とは異なる「もうひとつの日常」が、湯治場では体験できます。それこそが私たちが必要としている「ふるさと」であり、みんなで守っていく「場」なのです。
大沼さんのお話からは、湯治という伝統文化を現代人が求める癒やしへと橋渡しして、湯治場を守っていく情熱を感じました。
「百年ゆ宿 旅館大沼」の詳細情報
| 施設名 | 「百年ゆ宿 旅館大沼」 |
|---|---|
| 住所 | 宮城県大崎市鳴子温泉字赤湯34 |
| 電話番号 | 0229-83-3052 |
| アクセス | 東北道「古川IC」から車で約40分 JR陸羽東線「鳴子御殿湯駅」・ミヤコーバス「鳴子温泉赤湯」から徒歩約5分 |
| URL | http://www.ohnuma.co.jp/ |
※2020年10月1日現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日帰り入浴の受付を中止しています。
アフターコロナの温泉文化を考えるインタビュー
アフターコロナの温泉文化を考える①「1人の人間としての関係を」川島旅館3代目女将・松本美穂さん(北海道 豊富温泉)

安全で楽しい温泉旅行のために!温泉施設のコロナ対策ガイドライン
温泉施設のコロナ対策ガイドラインを要約してみた【日本温泉協会】